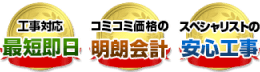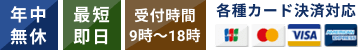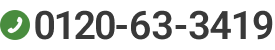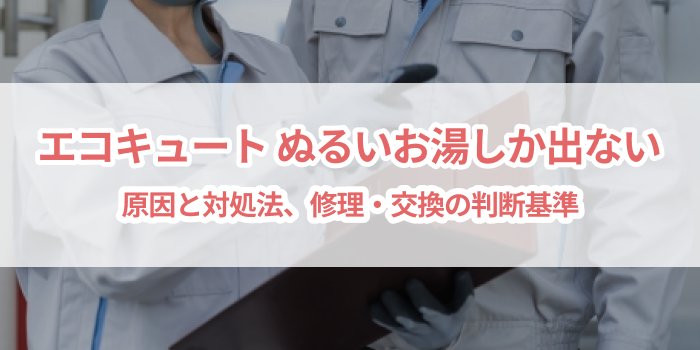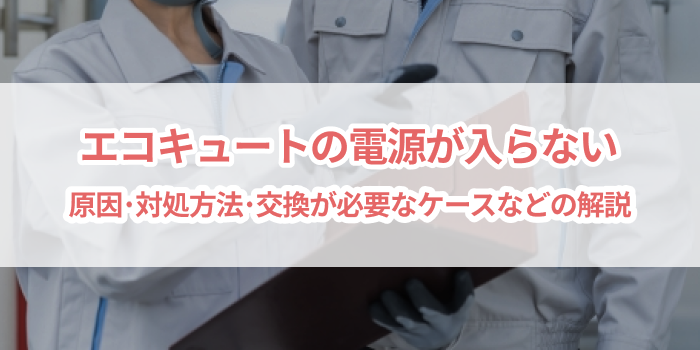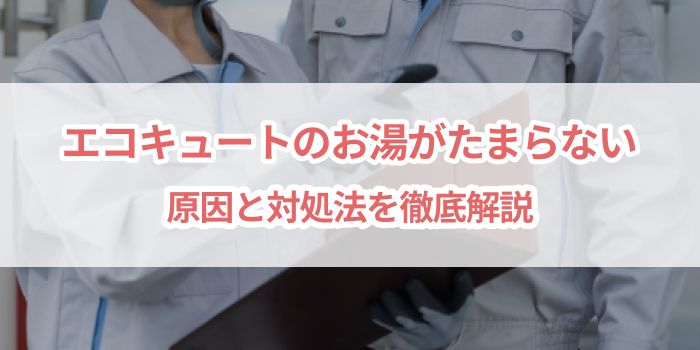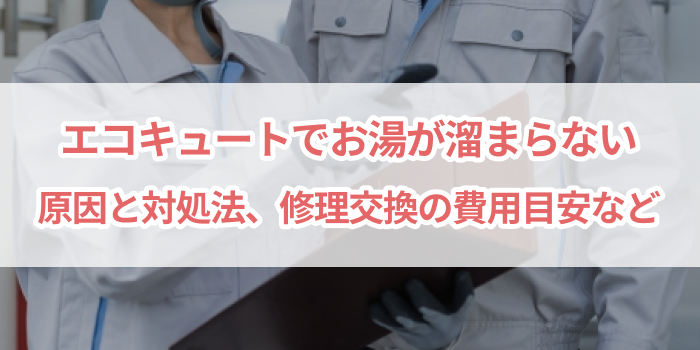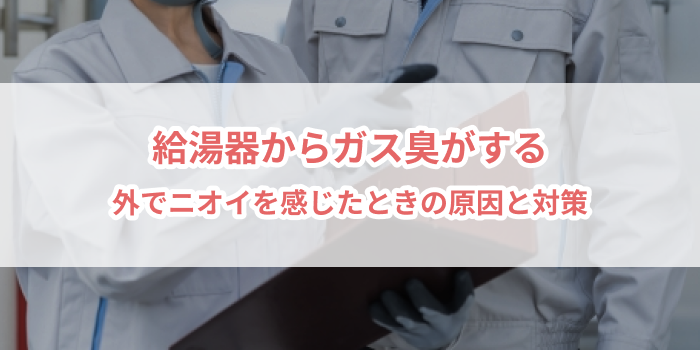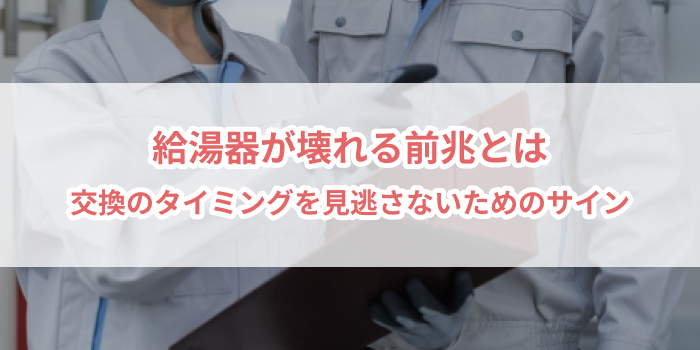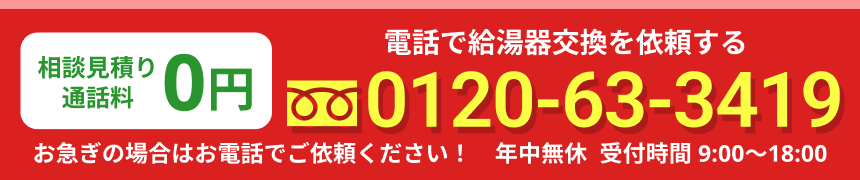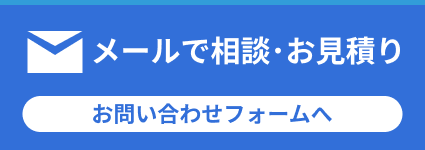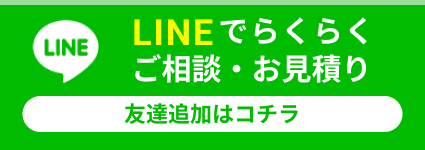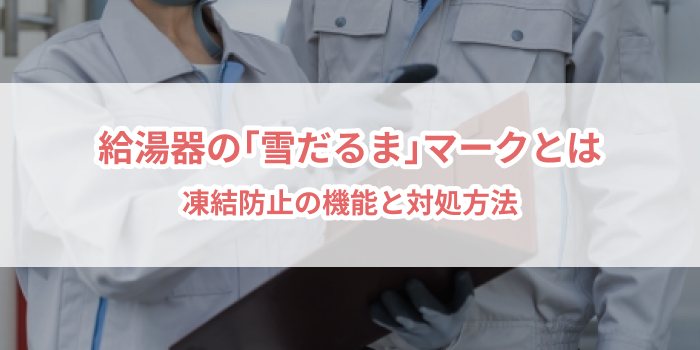
給湯器を使用している最中に、リモコンに雪だるまマークが表示された経験はありませんか? 雪だるまのマークは、給湯器の凍結防止機能が運転状態であることを示すサインです。
この記事では、雪だるまマークが給湯器リモコンに表示される原因と対処法、凍結を予防する方法などについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- 給湯器の「雪だるま」マークの意味
- 雪だるまマークが表示される条件
- 給湯器の凍結を予防する方法
給湯器リモコンの雪だるまマークとは
給湯器のリモコン画面に表示される雪だるまマークは、給湯器の凍結防止運転が作動していることをユーザーに示すものです。
凍結防止運転は給湯器にもともと備わっている正常な機能のひとつで、外気温が一定以下になると、給湯器は凍結を防止するためにヒーターやポンプなどを自動的に作動させます。
そのため、雪だるまマークがリモコン画面に表示されたときは、凍結予防運転が正常に機能していると判断できます。
したがって雪だるまマークは故障や不具合を表すものではないため、給湯器リモコンに雪だるまマークが表示されても、基本的には対処の必要はありません。
「雪だるま」、「雪の結晶」、「F」はすべて凍結防止運転
給湯器の凍結防止機能が作動している最中に、リモコンに表示されるマークは「雪だるま」マークではないことがあります。
「雪だるま」以外に表示されるのは、「雪の結晶」・「F」・「凍結予防」など。
例えば、ノーリツやパロマ製の給湯器が凍結予防運転を開始した際、リモコン画面に表示されるのは、「*」のような雪の結晶マークです。
リンナイの給湯器では、「雪だるま」マーク、または「凍結予防」の文字が表示されます。
東京ガスや大阪ガスなどガス会社から販売されている給湯器は、OEM製品のため、「雪だるま」・「雪の結晶(*)」・「F」など機種によって表示が異なります。(※OEM製品・・・他メーカーが設計・製造した商品を、自社ブランド製品として販売した商品のこと)
いずれも凍結防止機能が運転していることを表しますが、メーカーや機種によって表示内容が異なるため、詳細は取扱説明書をご確認ください。
凍結防止機能とは
給湯器の凍結防止機能は、外気温が低下した時に、給湯器内部や配管の水が凍結するのを防ぐための重要な機能です。
主な機能は「凍結予防ヒーター」と「自動ポンプ運転機能」の2つ。
凍結予防ヒーターは、現在販売されているほぼすべての給湯器に搭載されている機能で、外気温が0~3℃以下になったことを検知すると自動的に作動して給湯器内部の配管を温めます。
自動ポンプ運転機能は、追い焚き付きの給湯器に搭載されている機能です。
外気温が約5℃以下かつ、浴槽内の水が循環金具より5cm以上であることを検知すると、給湯器内部のポンプが浴槽内の水を循環させ、追い焚き配管内に残っている水を強制的に動かして凍結を予防します。
給湯器リモコンの雪だるまマークを消す方法
給湯器リモコンに雪だるまマークが表示された際は、故障や不具合が起きているわけではないため、基本的に対応の必要はありません。
雪だるまマークは凍結防止機能が運転中であることを示すもので、凍結防止機能は給湯器にもともと備わっている機能です。
外気温が5℃程度まで上がって凍結のリスクが低くなれば、凍結防止機能が自動的に停止し、雪だるまマークも消えます。
雪だるまマークが消えない場合
外気温が5℃以上になっても雪だるまマークや雪の結晶マークがリモコン画面から消えない場合、給湯器が不具合を起こしている可能性があります。
この場合は、以下の方法を試してみてください。
電源をリセットする
リモコンの電源を一度落とすか、給湯器本体の電源を入れなおしてみましょう。
一時的なトラブルであれば、リセット操作によって動作が正常となり、雪だるまマークの表示が消える可能性があります。
エラーコードを確認する
雪だるまマークが消えない場合、リモコンにエラーコードが表示されてないか確認してみましょう。
エラーコードは給湯器に故障や不具合が起きた際に、リモコン画面に表示される英数字のことです。
給湯専用給湯器は2桁、追い焚き付きふろ給湯器は3桁で表示され、コード番号を読み解くことでエラーの内容や発生箇所をある程度特定することができます。
エラーコードの番号を確認し、取扱説明書の解説に沿って適切に対処を行うことで、エラーが解除される可能性があります。
凍結が起きていないか確認する
給湯器が凍結を起こしていると、雪だるまマークが消えない場合がございます。
気温が上がって凍結した部分の氷が溶けると、雪だるまマークは自然に消えるため、基本的には自然解凍を待つのがおすすめです。
ただし、凍結によって給湯器が故障したり、配管が膨張して破裂したりした場合は、個別対応が必要となります。
給湯器の修理や交換を行う
電源リセットや凍結解消などの方法を試しても雪だるまマークが消えない場合は、給湯器が故障している可能性が高いです。
修理や交換などの業者対応が必要ですので、メーカーや専門業者にご相談ください。
注意点として、給湯器の修理交換はご家庭内で行うことはできません。
無資格者による給湯器の分解や修理は禁止されており、もし自分で修理して失敗した場合には、各保証の対象外となるリスクもございます。
そのため、給湯器の修理や交換を行う際は、必ずメーカーや業者に相談するようにしましょう。
給湯器の凍結防止機能が作動する条件
給湯器リモコンの画面に雪だるまマークが表示されるのは、凍結防止機能が運転状態になっているためです。
凍結防止運転が正常に機能していないと、外気温の低下時に機器内部や配管などが凍結を起こして故障するリスクがあります。
では、凍結防止運転はどのような条件下で作動するのでしょうか。
以下で詳しく解説いたします。
外気温が一定以下になる
外気温が一定以下になると、凍結防止機能は自動的に作動します。
作動温度はメーカーによって異なりますが、0~5℃以下が一般的な設定です。
例として、リンナイ製の給湯器の場合、気温が3℃以下になったことを検知すると、凍結防止機能が自動運転を開始します。
また、建物や塀などに囲まれて日当たりが悪い、冷たい風が通りやすい場所など、冷えやすい場所に給湯器が設置されている場合、外気温が0~5℃以下でなくても局所的に凍結が発生することもあるため注意が必要です。
給湯器の電源が入っている
給湯器の凍結防止運転機能を正常に作動させるためには、本体の電源が入っていることが必要条件のひとつです。
凍結防止運転が機能しないと、冬場や外気温の低下時に給湯器が凍結を起こし、故障する恐れがあります。
給湯器本体の電源プラグが抜けていたり、分電盤の電源が落ちていたりしないか確認するようにしましょう。
浴槽に十分な水量がある
追い焚き機能付きのふろ給湯器では、追い焚き用の配管の凍結を防止する「自動ポンプ運転」が搭載されています。
自動ポンプ運転は浴槽内の水をポンプ吸い上げて強制的に循環させるため、浴槽内の水は循環口より5cmほど高い位置である必要があります。
浴槽内に水が入っていないか、水位が循環口より低い位置であると、循環ポンプは空運転を起こして凍結したり異音がしたりすることがございます。
そのため、冬など冷え込む時期には浴槽内の水を循環口より5cm程度上になるよう残しておくようにしましょう。
給湯器の凍結を予防する方法
雪だるまマークが給湯器リモコンに表示された場合は、給湯器が自動的に凍結防止機能を作動させている状態ですので、凍結に対する特別な対処は必要ありません。
ですが、外気温がマイナス15℃以下になった場合や、日陰で風が当たりやすい場所に給湯器が設置されている場合、積雪時などでは、特に凍結のリスクが高まります。
給湯器の凍結を予防するには、凍結防止機能を正常に機能させることが重要です。
正しく凍結対策を行うために、以下の予防方法を取り入れてください。
給湯器の電源を切らない
凍結の対策方法・予防行動はいくつかありますが、特に重要なのが「給湯器の電源を切らない」ことです。
電源を切ってしまうと凍結防止機能が停止するため、気温が下がった時に配管が凍結を起こすリスクが高くなります。
もし凍結が原因で配管に亀裂が入る、破裂するなど破損して水漏れが起きた場合、業者による修理対応が必要となり、お湯が使えるようになるまで時間も費用もかかる恐れがあるのです。
そのため、凍結防止機能が作動している間は電源プラグを抜かず、給湯器の電源を切らないように注意してください。
浴槽内の水を循環口より5cm高くためる
追い焚き対応のふろ給湯器では、追い焚き用配管の凍結予防も大切です。
浴槽内に循環アダプターより5cm以上の水をためておくことで、給湯器の追いだきポンプが自動で水を循環させ、配管の凍結を防止することができます。
運転中は「ウーン」という音がしますが、正常な作動音ですので故障ではありません。
ただし、浴槽に水がないとポンプが空運転し、大きな音が発生することがあるため注意が必要です。
水道の蛇口を少し開けて水を流す
給水用配管の凍結を防ぐために、水道の蛇口を少し開けて水を細く流し続ける方法も有効です。
水は止まっているより動きがある状態の方が、凍結が起きにくくなります。
水量の目安としては、1分間に約400ミリリットル(水の幅が約4mm程度)の水を出し続けるのがおすすめです。
また、水を無駄にしないために、栓をして浴槽内に水を溜めておくと経済的ですが、浴槽から水があふれる可能性があるため長時間流しっぱなしにする際はご注意ください。
一般的な浴槽がいっぱいになるのは約240リットルで、毎分400ミリリットルの水を出し続けた場合、約10時間かかります。
凍結予防ヒーターを設置する
寒冷地にお住まいの場合や、日当たりが悪い位置に給湯器が設置されている場合など、凍結リスクが特に高い状況では、後付けタイプの凍結防止ヒーターを配管に巻く方法もおすすめです。
後付けタイプの凍結防止ヒーターにはサーモスタットが内蔵されており、気温の低下を検知すると電気を使用して配管を温めます。
給水配管、給湯配管、追い焚き配管など、給湯器外部の露出している配管に使用するもので、ホームセンターやインターネット通販サイトなどから購入可能です。
ヒーターは電気を使用するため、電源が必要となります。
また、必要以上に長いヒーターを巻いてしまうと余計な電気代がかかってしまうため、購入する際には配管の長さを確認するようにしましょう。
給湯器が凍結したときの対処方法
給湯器が凍結してしまった場合の対処方法は、氷を溶かすことです。
具体的には、自然解凍を待つか、ぬるま湯を使って氷を溶かす手法を用いるのが一般的な対処方法となります。
自然解凍を待つ
給湯器の配管に凍結が起きている場合、対処方法としては自然解凍を待つのが最もおすすめです。
気温の上昇を待つことで緩やかに配管内の氷が溶けるため、配管に負担がかかりにくく破損のリスクが低いためです。
ぬるま湯で凍結を解消する
すぐにお湯を使いたい場合は、ぬるま湯を使った応急処置を試してみてください。
手順は、給水元栓や配管など凍結している場所にタオルを巻き、約30~40℃のぬるま湯をゆっくりかけ、氷が溶けたことが確認できたらタオルを取って乾いた布で水分をきれいに拭き取るという流れとなります。
このとき、熱湯を使用すると配管に負担がかかって亀裂が入ったり破裂したりする恐れがあるため、必ずぬるま湯を使用してください。
また、ぬるま湯を掛けた後に配管に付着した水滴を残したままにすると、配管の外側で凍結が起きる可能性があるため、余分な水滴はキレイに拭き取るようにしましょう。
凍結を解消してもお湯が出ない、水漏れしている場合
凍結した部分の氷が溶けたのにお湯が出ない場合や、給湯器本体や配管から水漏れしている場合は、業者による専門的な対応が必要です。
配管が破裂したり亀裂が入ったりしている場合は、部分的な配管修理で済みますが、給湯器の内部部品に不具合が起きている場合は、本体ごと交換が必要なケースもございます。
10年以上使用している給湯器が故障した場合は、耐用年数を過ぎていることから修理部品が入手できず、交換対応となります。
いずれにせよプロによる対応が必要ですので、早急にメーカーや専門業者に連絡することをおすすめいたします。
給湯器リモコンの「雪だるま」マークについて まとめ
給湯器リモコンに雪だるまマークや雪の結晶マークが表示された場合、給湯器が「凍結防止機能」を作動させていることを示しています。
凍結防止機能は冬季など気温が低下した際に、給湯器本体や配管を凍結から守るための重要な機能であり、故障や異常を示すものではありません。
ただし、気温が上がっても雪だるまマークが消えない場合は、給湯器の故障や不具合が疑われるため、業者による修理や交換が必要となるケースもございます。
給湯器の雪だるまマークが消えない、本体や配管から水が漏れている、お湯が出ないなど、給湯器トラブルでお困りの際は「給湯器交換のユプロ」にご相談ください。
ユプロは給湯器の交換取り付けの専門業者で、365日年中無休・最短即日での出張工事に対応しております。
取り扱いメーカーはノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパスほか国内正規品のみ。
省エネ給湯器のエコジョーズやエコキュートなども低価格でご提供しております。